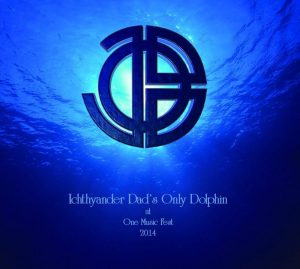(こちらもウクライナの良作プログレなので再掲です)
ウクライナのグループの1st、1998年作。
出だしから Pat Metheny + Jan Garbarek と言った雰囲気ではじまるウクライナのフュージョングループです.とは言っても、それだけの言葉では語れない繊細で美しい音楽です。
ライナーのメンバー紹介が読めないので、どれだけのメンバーと 楽器が参加しているのか分からないのですが、結構たくさんの楽器が演奏していると思います。しかし、参加楽器全部が一挙に演奏して重厚さを出すと言う感じではなく、いくつかの楽器で繊細で美しい演奏を聴かせた後に、コロッと楽器編成が代わってまた美しい演奏が続くという部分も多く見られました。
例えば、出だしが民族楽器 (?) ではじまるエキゾチックな感じの 演奏で、途中からピアノやリコーダーによる美しい演奏に移行すると いう曲がいくつかありました。そのエキゾチックさとその後の美しい 演奏の変化が、意外な感じをあまり与える事なく、しかし曲がだらだらとした演奏になるのを防いでいるような感じもします。
ヴァイオリンは独特な演奏で、リコーダーが叙情的な雰囲気を良く出しているが、ピアノの美しさとサックスの透明感ある美しい演奏 (Garbarek 的) が印象的です。
全体的に叙情的で非常に美しい曲が多く、それにエキゾチックな雰囲気がオリジナリティを与えています。演奏レベルも文句なしで、満足の一枚でした。
(1999年に書いたレビュー)